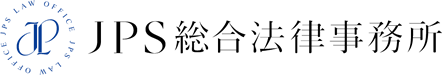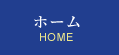依頼を受けた当事務所所属弁護士が、その労働組合がどのような労働組合かをご説明したうえ、今後の進み方についてご説明した。.....
経営者からのご質問
「当社は、従業員について、年俸制を採用しており、年俸に残業代を含む趣旨の雇用契約を締結しています。当社に、残業代支払義務が生じる可能性はありますか。また、可能性があるとして、年俸の金額が2000万円の場合もダメでしょうか」
ご質問に対する当事務所の回答
1 年俸制を採用している会社であっても、時間外労働が発生している場合には割増賃金を支払う必要性があります。
また、2000万円という高額な年俸が設定されている従業員の場合であっても、原則として割増賃金を支払う必要があるでしょう。
さらに、年俸に残業代を含む趣旨の雇用契約を締結していたという経緯があったとしても、この趣旨の合意の有効性が認められるためには、一定の要件を備える必要があり、直ちに有効なものとはいえません。
2 一方で、当然のことではありますが、管理監督者(労基法41条)の要件を満たしている場合や、裁量労働制(労基法38条の3等)を採用している会社であれば、残業代を支払う必要性はありません。
解説
1 年俸制と割増賃金
年俸制とは1年間にわたる仕事の成果によって翌年度の賃金額を設定しようとする制度になります。つまり、賃金額の決定について「労働時間」が大きな基準とはなっていない制度であり、年俸制を採用している会社の経営者の方々のなかには年俸制を採用している以上は残業代を支払う必要性がないものと理解している方もおられます。
しかし、このような理解は誤りです。年俸制それ自体は、労基法37条が定める「時間外労働、休日出勤をした労働者には割増賃金を払わないといけない」という大原則を免れさせる効果を持つものではありませんので、管理監督者ないし裁量労働制の要件を満たさないかぎり、会社は割増賃金の支払義務を負うことになります。
2 過去の裁判例
⑴ システムワークス事件(大阪地判平14.10.25/労判844号79頁)においては、年俸制を採用している従業員からの割増賃金の請求について、裁判所はこれを認めています。
⑵ この事件においては、年俸制の枠組みの中で7月と12月に一般的な会社でいう「賞与」のような金員を支給していたのですが、裁判所はこの金員は「賞与または賞与に準ずる性格を有するとは認められない」と判断し、割増賃金を計算する際の基礎となる賃金に参入しました。
一般的な「賞与」の場合、「臨時に支払われた賃金」ないし「一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」にあたり、割増賃金の基礎となる賃金には参入されないところ、この裁判においては上記の7月と12月の金員も算入されることとなり、会社にとってかなり不利な結果となりました。
⑶ また、上記の事件においては、会社は「月に支給する賃金のうち3万円は時間外手当として定額支給していたので、その部分は既払いである」とも主張しましたが、①採用時にその旨の説明がなかったことや②給与明細書の3万円を残業代とする旨の記載は会社が一方的に作成、交付したものであることを理由に会社の主張を認めませんでした。
裁判例では固定残業代が有効なものとして認められるためには、それが残業代としての「対価」であることを前提として、雇用契約の内容となっている必要があるとされていますが、本裁判例もそのような一連の裁判例の流れに沿ったものといえるでしょう。
3 高額な年俸
モルガン・スタンレー・ジャパン事件(東京地判平成17年10月19日労判905号5頁)では、月額にして約183万円の高額な年俸を得ていた従業員からの割増賃金請求について、高額であるが故に基本給部分と割増賃金部分の区別がないままに基本給に割増賃金を含むとしても労働者の保護に欠けることはないとして、労働者の割増賃金請求を否定した事案です。
これに続く医療法人社団康心会事件(最判平成29年7月7日労判1168号49頁)は、年俸1700万円の医師からの割増賃金請求について、第1審、第2審がモルガン・スタンレー・ジャパン事件と同様の枠組みで年俸への割増賃金組み入れを認めたのに対して、最高裁が高額な年俸であっても通常の賃金部分と割増賃金部分の判別が出来なければ基本給部分への割増賃金の組み入れは認められないと判断しました。
よって、年俸が高額であったとしても、その年俸のうち、どの部分が割増賃金相当額なのか判別できなければ、「年俸に割増賃金を含む」という合意は認められません。
注意すべき点
1 年俸制の採用で割増賃金の支払いを免れることはできません。裁量労働制や固定残業代等のその他の方法を用いて対策を練るべきです。
2 年俸として支払う給与に、一定時間分の時間外労働割増賃金や休日労働割増賃金の支払いを含めたいのであれば、給与のどの部分が基本給部分で、どの部分が時間外労働割増賃金部分か従業員にわかるように明確に分けて設定し、就業規則、労働契約、毎月の給与明細などで書き分けることが重要になります。
もし、区別が不十分であるとされた場合、その割増賃金として支払っていたつもりの部分は割増賃金の支払いとしては認められず、逆に割増賃金の基礎となる賃金の金額が上がることとなり、弱り目に祟り目といったことになってしまいます。
コラムの最新記事
労務問題の最新記事
-
コラム2024/12/26
-
コラム2024/12/20
-
コラム2024/08/23
-
解決事例2024/05/27