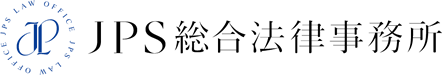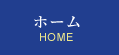依頼を受けた当事務所所属弁護士が、その労働組合がどのような労働組合かをご説明したうえ、今後の進み方についてご説明した。.....
労働審判とは
労働審判は、解雇や給与の不払いなど、労働関係のトラブルを迅速かつ適正に解決するために、平成18年4月に司法制度改革の一環として誕生した制度です。現在、裁判所に年間3,500件から4,000件の申立てがなされています。
労働審判の特徴としては、①労働関係の専門家による関与、②迅速な手続、③事案の実情に即した柔軟な解決、④異議申立てによる訴訟移行、の4つが挙げられます。
具体的には、①労働審判は、裁判官1名と労働審判官2名で組織する労働審判委員会が行います。労働審判官は、雇用関係の実情や労使慣行に関する詳しい知識と豊富な経験を持つ者の中から任命され、中立かつ公正な立場で、審理・判断に加わります。
②労働審判は、原則として3回以内の期日で審理を終えることになっているため、迅速な解決が期待できます。裁判所の統計では、平均審理期間は81.2日であり、66.9%の事件が申立てから3か月以内に終了しています。
③労働審判では、まずは調停という話し合いによる解決を試み、話し合いがまとまらない場合に、事案の実情に即した労働審判という判断を行います。
④労働審判に不服のある当事者は、異議申立てをすることができます。異議申立てがなされた場合は、労働審判は効力を失い、訴訟手続に移行します。
労働審判の終わり方としては、令和2年の裁判所の統計では、審判が16.2%、調停成立が68.1%となっており、和解という形で事件が終わることが多い状況となっています。
どういった場合に労働審判を申し立てられるのか?
労働審判は、労使間の個別的な紛争を解決する手続です。裁判所に申し立てられる事件の種類としては、解雇無効(地位確認)と残業代請求(賃金請求)の2つが事件の大部分を占めています。
1 解雇無効(地位確認)関連の事件
会社が労働者を懲戒解雇や普通解雇した場合に、対象となった労働者が「解雇は無効なので労働者としての地位が継続している」と主張して、労働審判を申し立てるケースです。令和2年に申し立てられた全事件のうちおよそ半数の約1900件がこの解雇関係の事件でした。
この解雇関連の事件の場合、当該労働者が会社に復職するという形での解決が多いように想像されますが、実際は当該労働者の退職を前提に会社が解決金を支払うという形で解決するケースが一般的です。そして、労働審判の審理の過程において、労働審判委員会が解雇は無効であるという心証を抱いた場合は解決金が高額となり、解雇は有効であるという心証を抱いた場合は解決金が低額となる傾向があります。
解雇が無効である可能性が高い事件は賃金3か月から6か月分以上の解決金、解雇が有効である可能性が高い事件は賃金1,2か月程度の解決金となることが多いようです。
2 残業代請求の事件
時間外労働に対する未払賃金を求める事件です。既に退職している従業員から申し立てられるケースが一般的ですが、在職中の従業員から労働審判を申し立てられるケースもたまに見受けられます。
この残業代請求の事件の場合も和解で解決するケースが多いです。ただ、正確な残業代の計算には労働時間の把握などに多くの時間を要しますが、労働審判は短期間で終えることが予定されているため、会社側は短期間のうちに正確な事案の把握が求められます。
労働審判の流れ
1 申立て
労働審判を申し立てるためには、地方裁判所に申立書を提出する必要があります。
↓
2 期日指定・呼出し
労働審判官は、特別の事由がある場合を除き、申立てがされた日から40日以内の日に第1回の期日を指定し、当事者双方を呼び出します。また、相手方には、期日呼出状と共に、申立書の写し等が送付されます。
↓
3 答弁書の提出
相手方は、労働審判官が定めた期限までに、答弁書を提出しなければなりません。
↓
4 期日における審理
労働審判委員会は、原則として3回以内の期日の中で、事実関係や法律論に関する双方の言い分を聴いて、争いになっている点を整理し、必要に応じて申立人(労働者)や相手方の関係者(会社の代表者や従業員)などから直接事情を聴取するなどの審理を行います。また、話し合いによる解決の見込みがあれば、いつでも調停を試みます。
↓
5 調停成立
話し合いがまとまると、調停が成立し、手続は終了します。調停の内容は調書に記載され、条項の内容によっては、強制執行を申し立てることもできるようになります。
↓
6 労働審判
話し合いがまとまらない場合は、労働審判委員会が、審理の結果認められた当事者間の権利関係と手続の経過を踏まえ、事案の実情に即した判断(労働審判)を示します。
労働審判に対して2週間以内に異議の申立てがなければ、労働審判は確定し、その内容によっては強制執行を申し立てることもできるようになります。
一方、労働審判に対して2週間以内に異議の申立てがなされれば、労働審判は効力を失い、訴訟手続に移行します。
労働審判を申し立てられた時のポイント
労働審判は、原則3回という短い期間で終了することが予定されているため、1回目の期日で和解についての大枠の方針を決め、2回目以降の期日では和解の内容についての話し合いを進めていくという流れが一般的です。
そのため、会社側の立場からすると、反論の機会は、実質的に見れば、答弁書と1回目の期日に限られているところ、その少ない反論の機会のなかで労働審判委員会に事案を正確に理解してもらうためには、内容の充実した答弁書を作成できるか否かが最大のポイントになります。
従いまして、労働審判における答弁書には、会社側の主張を余すことなく、かつ、具体的に記載することが重要になります。通常の訴訟においては、答弁書はあっさりとした内容とし、その後に提出する準備書面で詳細な主張や反論を追加していくということがよく見受けられますが、労働審判においてはこの方法は通用しません。第1回期日の前に提出する答弁書の中に会社として主張反論したいことのすべてを記載しておく必要があります。
解雇関係の事件では、解雇に至った事実関係はもちろんのこと、客観的に合理的な理由があったこと、手段も相当であったことを丁寧に主張する必要があります。また、残業代請求の事件では、労働時間についての主張のほか、具体的な計算シートなどを準備することも必要となります。
労働審判について弁護士に依頼するメリット
繰り返しになりますが、労働審判における会社側の防御手段としては答弁書の作成が最大のポイントになります。
もっとも、労働審判はある日突然申し立てられることが多く、裁判所が指定する答弁書の提出期限は会社にとって非常にタイトな日程であることが多いです。
業務が忙しいことを理由に内容のない答弁書を提出してしまう場合もあろうかと思いますが、これでは良い結果が得られるはずもなく、不当に高額な解決金を支払うことになってしまうなど、会社に大きな損害が及んでしまうこともあり得ます。
弁護士に依頼すれば、充実した答弁書の作成はもちろんのこと、期日において会社側の参加者の発言をサポートしてもらえるなど、十分な防御を行うことが可能となります。
弁護士に依頼するかどうかは、最終的には、自分の意思で決めていただくことになりますが、必要に応じて、法律の専門家である弁護士に依頼することが望ましいことは明らかです。
なお、日弁連の統計では、当事者の双方ないし一方に代理人が選任されている事件の割合は90%を超えており、労働審判においては弁護士を選任することが一般的となっています。
労働審判について弁護士が詳しく解説の関連記事はこちら
-
コラム2024/12/26
-
コラム2024/12/20
-
コラム2024/08/23
-
解決事例2024/05/27